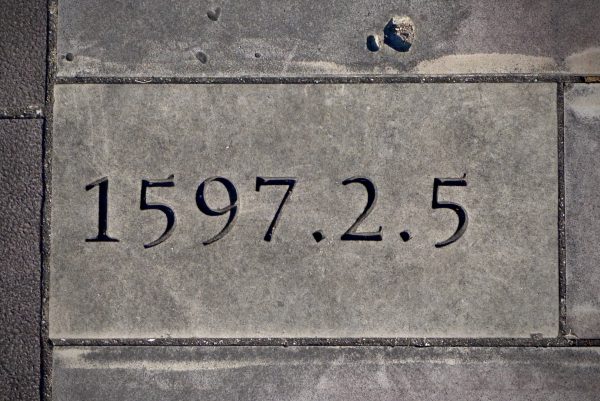It’s a new dawn
It’s a new day
It’s a new life
For me
And I’m feeling good
-Feeling good / Anthony Newley and Leslie Bricusse-
インドの古くからの哲学によると、日の出や日の入り前後の時間帯は、一日のなかで最も神聖な時間とされていて、瞑想や創造活動をするのによいのだそうです。
黎明の青い薄明かりから次第に空が明るくなり、太陽が昇ると、思わず掌を合わせたくなります。
誰もが新しい夜明け、新しい一日、新しい人生を希望をもって生きていかれるように願っています。
起きて見てください
この美しい夜明け
希望をもたらす
新しい夜明け
Acorde para ver
Este lindo alvorecer
Trazendo esperança
de un novo amanhecer
–Novo Amanhecer / Emilio Dias-